ストレスの原因として語られることが多い「人間関係」。
果たして、その正体はなんなのでしょうか。
この記事では、書籍「SOLO TIME ひとりぼっちこそが最強の生存戦略である」に学ぶ
人間関係ストレスの正体、そして人生の活力を充電する方法についてご紹介してきます。
- 私たちを疲弊させる「群れ」の正体
- 「ひとりぼっちの時間=SOLO TIME」が重要なワケ
- 人生の活力を取り戻すための2つの行動

【この記事を書いた人】
- 2021年10月ブログ開始。記事執筆数80本以上。
- サラリーマン。副業としてブロガー活動。
- 1か月の読書は5~6冊。
- Twitter:@Beyond-s16
著者は精神科医・名越康文さん
著者は、精神科医の名越康文さん。
現在は日テレ系「シューイチ」など、TVコメンテーターとして見かける日も増えてきました。
初めて名越さんの存在を知ったのは、ラジオ出演の時。
軽妙な語り口で話す人だなぁと思ったのを覚えています。
この書籍も、名越さんが心理学講座で語るように、口語で書かれていて
サクサクと読み進められました。
群れの中にある私たちを疲弊させるもの

私たちは日々何かの集団(=群れ)の中で生きています。
身近なところなら「職場」や「家庭」、世界規模で見れば「日本人」という群れです。
群れに所属するということは、「その群れのルールに束縛される」ことにつながります。
職場ならば「上司の機嫌を損ねないように」「空気を読んで」といった言葉をよく聞きます。
そうした気遣いで群れの中でのあなたの地位は向上するかもしれません。
しかし、群れの中での地位を守ること、さらに上げることが目的になってしまうと、
そのために大きなストレスを背負い続けることになります。
書籍「ひとりぼっちこそが最強の生存戦略である」は、
こうした人間関係のストレスから自分を解き放つために
「ひとりぼっちの時間=SOLO TIME」で自分を見つめることが大切と説いているのです。
「ひとりぼっち」には2つのパターンがある
あなたは「ひとりぼっち」という言葉に、さびしさや孤独感を感じますか?
「ひとりぼっち」を英語に翻訳すると、Alone または Lonelyとなります。
Aloneは物理的な1人の状態を表すのに対し、Lonelyは孤独などネガティブな意味を持ちます。
日本語の「ひとりぼっち」はLonelyに近い意味合いで取られる場合が多いですね。
適応過剰にならないための「SOLO TIME」

Lonelyが意味するところは、人間が所属する群れを失うことに恐怖を感じているということです。
つまり、群れの力に頼っている部分が少なからずあるということです。
職場の人間関係などにストレスを感じている時。
職歴に穴を空けないために、今の仕事を続けなくてはと感じている時。
群れからの期待に応えたり、居場所を確固たるものにするために、
自分を消耗させてしまってはいけない。
むしろ、群れの期待とは別に「自分は好きに生きる」と思える時間を作ることが救いになります。
Aloneを感じられる瞬間、つまりSOLO TIMEを持つことで自分を見つめ直しましょう。
人生の活力は「SOLO TIME」に充電する
職場や家族の人間関係に疲れたり、傷ついてしまった時は、
「群れ(人間関係)の外に出て充電すること」がオススメです。
書籍の中では次のように推奨されています。
職場や家族の人間関係に少し疲れた時には、軽い山歩きや、あるいは季節の折々に花が咲く公園にでも出かけて行くのも良いでしょう。
「第1講 あなたは群れの中で生きている」より引用
普段自分が過ごしている「場」や「空気」の影響は、思っている以上に大きいものです。
テレワークが普及して距離を取れたおかげで、今の仕事を続けられているという話も耳にします。
これらの影響から離れて過ごさない限り、群れの疲れを癒すことはできないもの。
意識的に離れる時間を作ることがポイントですよ。
フィクションの世界ですが、「八月の六日間」という小説では、人間関係に疲れた主人公が山へ行く姿が描かれています。
当ブログでも紹介しているので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
群れの中で充電しても活力は産まれない
例えば、職場の上司との人間関係に疲れて、同僚に癒してもらうことはできるでしょうか。
同じ職場、似たような思考の人は「わかってくれる」でしょう。
しかし、頭の中から仕事を完全に追い出してくれることはありません。
つまり、萎えた心を癒そうとしても、活力を充電することにはつながりにくいのです。
「SOLO TIME」の疑似体験は2つ
そうは言っても、ひとりぼっちの時間を作るのが難しいこともあります。
家族がいる、仕事が忙しい、理由はさまざま。
そんな時にも「SOLO TIME」を疑似体験する方法が2つあります。
それは、「①旅に出る」「②掃除をする」です。
1つずつ見ていきましょう。
①旅に出れば周りの人と環境が変わる

旅に出ることで、自分を取り巻く人も環境も変わって刺激を受けることができます。
著者の名越さんによれば、「可能なら一人で、3~4泊以上の旅に出るのがオススメ」と紹介しています。
1人で旅先に行けば、周りにいるのは普段一緒にいる人たちではありません。
そして、周りにあるモノも家や職場で私たちを囲んでいるものから変化します。
人間は周りの人・モノから影響を受けながら生きています。
1つの集団(群れ)に長く居続けると、集団の中の問題ばかりに目が行きがちになり
人生の活力を奪うことにつながっている場合もあります。
旅に出る、つまり群れから離れる感覚を体験することで、
1人で考え生きる時間の楽しみと覚悟についてゆっくりと考えられると良いですね。

「通ったことのない道をドライブする」とかでも効果ありそうだな。
(経験談)1人旅は効果を実感できる
私自身、1人で海外に10日ほど行ったことがあります。
1年くらい、周りの期待に振り回されたり、群れから孤立させられたり。
そんな状況で行った海外は、まさに「SOLO TIME」。
自分がしたいこと、譲らないことがはっきりとする時間でした。
当時1人暮らしで、休日はSOLO TIMEを過ごしていると思っていましたが、
旅の力はもっと偉大です。
世の中が落ち着いたらぜひ行きましょう。
私が1人で行ったデンマーク、紹介記事も書いているので、
最後まで読んでみてくださいね。
②掃除にも同じ効果が

仕事で責任あるポストについている、子どもがまだ小さい、感染症のリスクが怖い。
旅に出たくても出られない時は、「部屋の掃除」をしてみましょう。
著者の名越さんによれば、旅行と掃除の共通点は「モノを手放す」という行為だそうです。
それまでの自分を手放し、新しい自分に出会うために、掃除も効果的なので
休日やスキマ時間に「3分だけやってみる」から始めてみたいですね。
終わりに
この記事では、書籍「SOLO TIME(ソロタイム) ひとりぼっちこそが最強の生存戦略である」に学ぶ人生の活力の取り戻し方をご紹介しました。
以前、当ブログで紹介した小説「八月の六日間」の中では、「辛いことがあった時こそ山に行く」という描写がありました。
なんで?と思っていたところにこの本と出会って、「あぁ、小説の主人公は活力を取り戻しに行っていたんだな」と納得。
こうして記事で紹介することにしました。
気が萎えてしまうこともあるかもしれませんが、そんな時こそ「SOLO TIME」を手に入れて
人生の活力を充電しましょう。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
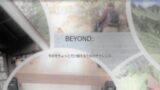



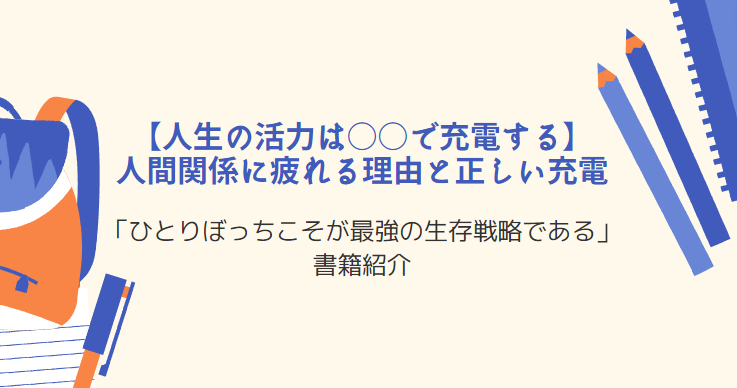


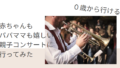

コメント