「美意識」には、人がそれぞれ持っている物事に対する態度や価値観が強く反映されます。
一見、「エリート」という言葉とは結び付かないようにも感じますが、
現代ビジネスでは複雑な意思決定が求められるもの。
そんな意思決定に直面したとき、個人の持つ「美意識」が大きな意味を持ちます。
この記事では、書籍『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?~経営における「アート」と「サイエンス」』から、美意識を鍛える意味、鍛え方をご紹介します。
- 「美意識」を鍛える必要が出てきている理由
- 美意識の鍛え方は3つ+ブログ主が考える鍛え方1つ

【この記事を書いた人】
- 2021年10月ブログ開始。記事執筆数100本以上。
- サラリーマン。時々、ブロガー活動。
- 1か月5~6冊の読書から厳選して紹介中。
- Twitter:@Beyond-s16
なぜアートが注目されている?

書籍『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』では、
そもそも現代のビジネスパーソンが直面している課題を次のように表しています。
これまでのような「分析」「論理」「理性」に軸足をおいた経営、いわば「サイエンス重視の意思決定」では、今日のように複雑で不安定な世界においてビジネスの舵取りをすることはできない
「忙しい読者のために」より引用
さらに、現代の企業・ビジネスパーソンへの取材から、大きく3つの理由からアートへの注目が高まっていると説明しています。
1.論理的・理性的な情報処理スキルの限界が露呈しつつある
2.世界中の市場が「自己実現的消費」へと向かいつつある
3.システムの変化にルールの制定が追いつかない状況が発生している
「忙しい読者のために」より引用
正解のコモディティ化が進んでいる
MBA(経営学修士)や論理思考・分析思考など、ビジネスに必要とされるスキルはさまざま。
こうしたスキルを紹介した本やセミナーは、webで調べると比較しなければ決められないほど、たくさん出てきます。
言い方を換えれば、
「多くの人が同じ方法論を学んでいて、同じ政界にたどり着くスキルを持っている」
状態が広がっているのです。
この状態は「正解のコモディティ化」と呼ばれ、
世界中の多くの市場が、この問題に直面しています。
「新しい企画や製品には、差別化が必要」と叫ばれる反面、思考法は共通。
この問題の打開策として、個々人の美意識=アートによる差別化が期待されているのです。
自己実現欲求を刺激するビジネスが必要
日本でも「モノ消費」から「コト消費」へ、というキーワードで知られるように
現代は、承認欲求や自己実現欲求を刺激するビジネスが必要とされています。
精緻なマーケティングスキルを用いて論理的に機能的優位性や価格競争力を形成する能力よりも、人の承認欲求や自己実現欲求を刺激するような歓声や美意識が重要になります。
「忙しい読者のために」より引用
文中で書かれているのは、どちらかと言えば「BtoC(企業 対 消費者)」ビジネスを対象にしているものと思います。
しかし、「B to B(企業 対 企業)」ビジネスでも、アートを身に付ける効果は大きいと考えます。
先述の「」への対策、
そして後述の「」という2つの目的で、アートを身に着ける効果は大きいと考えます。
ルールよりも先にシステムが変化していく
AI技術やメタバースなど、インターネットなどの仮想空間内での「コミュニケーション」や「所有」という概念が生まれています。
こうしたシステムは、ルールがこれから後追い的に制定されていくことになります。
(現在のように変化の早い世界について)そのような世界において、クオリティの高い意思決定を継続的にするためには、明文化されたルールや法律だけを拠り所にするのではなく、内在的に「真・善・美」を判断するための「美意識」が求められることになります。
「忙しい読者のために」より引用
新分野に踏み出すときには、「ルールで明文化されていないからOK」ではなく、
自分の持つ「美意識」に照らして判断する態度が求められるのです。
美意識の鍛え方4選
では、具体的な「美意識の鍛え方」についてみていきましょう。
絵画を見る

海外の有名美術館では、早朝からキュレーター(学芸員)が館内を案内するツアーを実施しています。
近年では、早朝のツアーに出勤前のビジネスパーソンがやってくることも少なくないことが本書の中で紹介されています。
科学的に証明される絵画鑑賞の効果
エール大学の2001年の研究によれば、
絵画を見ることで細部に気づく力や観察能力が10%向上したとも言われています。
文章や数式のように、定型化されていない情報を読み取ろうとする絵画鑑賞。
観察能力を高めていくことが、重要な局面の意思決定でも効果的なことが期待されます。
文学を読む
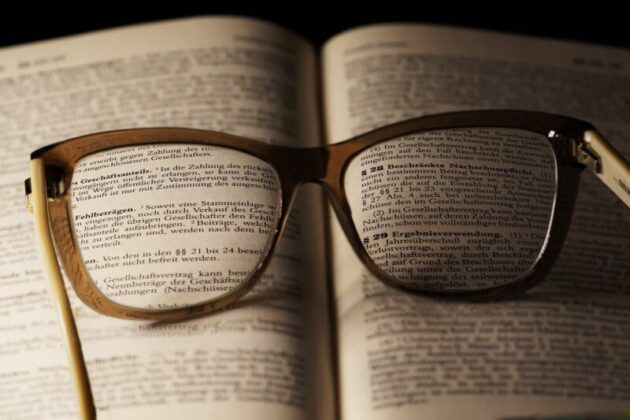
文学を読むのも、効果的なトレーニングです。
文学と美意識が繋がる理由は、本書の中で次のように述べられています。
古代ギリシアの時代以来、人間にとって、何が「真・善・美」なのか、ということを純粋に追求してきたのは、宗教及び近世までの哲学でした。そして、文学というのは同じ問いを物語の体裁をとって考察してきたと考えることができます。
第7章 どう「美意識」を鍛えるか? より引用
例えば、小説形式で書かれている文学の場合。
複数の登場人物が出てきますね。
【小説で注目すべきポイント】
それぞれの人物について描かれる価値観の中で、自分がもっとも共感するのはだれか。
自分が持つ「真・善・美」に照らして共感を感じることや、
別の価値観に対して理解に努めることが、自分の感度を高めていくことにつながります。
詩を読む
「詩を読む」という行為は、日常とはかけはなれているかもしれません。
しかし、本書では、リーダーシップと詩のつながりを次のように説いています。
確かに、リーダーシップと「詩」には非常に強力な結節点がある。それは何かというと、両者ともに「レトリック(修辞)が命である」という点です。
第7章 どう「美意識」を鍛えるか? より引用
あなたがリーダーの立場にあるならば、
スピーチやミーティングで言葉の力が求められます。
もしあなたが語る言葉を持っていないとしたら、部下への求心力を下げることにもつながりかねません。
詩は、多くの比喩を使って表現をしています。
比喩は、多くを語らなくとも、言わんとすることを伝える力を発揮してくれるのです。
筆者が考える鍛え方
本書で紹介している以外の美意識の鍛え方として
私が効果を感じるのは「音楽鑑賞」です。
また、クラシック音楽のように同じ曲を別のオーケストラが演奏するならば
聞き比べると、必ず違いがあります。
間合いの取り方や、曲の速さの違いを実感できますよ。
終わりに
ビジネススキルに関する本や、セミナーは多岐に渡って存在します。
裏を返せば、「同じような結論にたどり着ける教育を受けた人がたくさんいる」ということです。
経験や理論がベースの意思決定では、現代ビジネスで差別化をしていくことはほぼ不可能です。
自らが持つ感性を磨き、真似できないオリジナルなものを生み出していきましょう。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
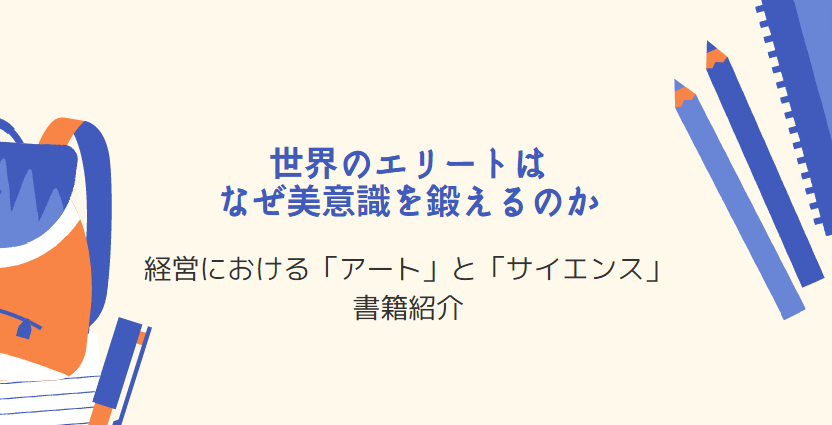



コメント