スポーツや音楽、様々な趣味を楽しむには身体を上手に使うことが求められます。
もし、身体のつくりに合わない動きで無理をすれば、ケガや不調につながることも。
だからこそ、自分の身体について理解しておくことは重要です。
この記事では、音楽家向けに開発された「アレクサンダー・テクニーク」について、ご紹介していきます。
参考にしているのは、こちらの本です。
- ボディ・マッピングとアレクサンダー・テクニークとは?
- 楽な姿勢のつくり方

【この記事を書いた人】
- 2021年10月ブログ開始。記事執筆数80本以上。
- サラリーマン。副業としてブロガー活動。
- Twitter:@Beyond-s16
ボディ・マッピングとアレクサンダー・テクニークとは?
そもそもボディ・マッピングとアレクサンダー・テクニークは次のような意味を持ちます。
ボディ・マッピング=自分の身体の構造を理解する
ボディ・マッピングを覚えると、、自分の身体がどんな構造か理解できるようになります。
「当たり前じゃん!」と言いたくなると思いますが、
自分ではできているつもりでも、違う動きをしていることってありませんか?
極端な例かもしれませんが、
テレビで「運動神経悪い芸人」を見ていると
バスケのレイアップシュートしているつもりだけど、全然違う動きになっていますよね。
自分の身体のつくりや、どう動かしているか、思い込みにしたがってしまうことで、
そのようなことが起こります。
ボディ・マッピングは、自分の身体の構造、そしてどんな動かし方をしているかを
理解することにつながります。
アレクサンダー・テクニーク=自分のクセを直していくこと
ボディ・マッピングで身体の構造や動きを理解しても、そのまま動かせるとは限りません。
人間には、それぞれクセがあるからです。
気の置けない友達と話している時は、大きい声が出るけれど
職場や緊張する場所に行くと、出しているつもりでも声が小さいと言われる。
こんな経験があるかもしれません。
これも一種のクセで、喉や首が緊張することで、思っているよりも声が小さくなってしまうんですね。
アレクサンダー・テクニークの開発者、F・M・アレクサンダーも、
舞台に立つと声がうまく出ない理由が、クセであることを発見して研究を始めました。
気になるクセがある人は、少しでも読んでみると良いかもしれません。
楽な姿勢のつくり方
楽な姿勢は、身体の構造にとって理にかなっていることばかりです。
1つ例を挙げましょう。
「まっすぐ立った自分」を横から見ている状態をイメージしてみてください。
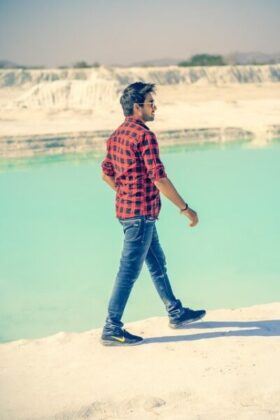
こんなイメージですね。
さて、首が楽な位置ってどこでしょう?
①横から見て、「自分の胸」の真上に「首の後ろ側」がくる。
②横から見て、「自分の胸」の真上に「首の前側」がくる。
正解は、②です。
頭は人間の身体の中でも特に重たい部分。
①の状態だと、頭の重さを支えるために、首の筋肉をたくさん使います。
このように、アレクサンダー・テクニークを使うことで理にかなった身体の姿勢を覚えていくこともできます。
まとめ:身体が楽になる気づきが見つかるかも
この記事では、ボディマッピングとアレクサンダー・テクニークについて、ご紹介しました。
参考にした本は楽器を演奏する人向けですが、
スポーツや日常生活の中で必ず動かす「身体」を扱っています。
どんな人にとってもヒントになることが詰まっていますよ。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。






コメント