登山前のトレーニングというと、荷物を背負って散歩などがありますが、
仕事や育児で忙しいと時間が取れないことも。
登り始めてからバテないようにするためには、安定したフォームをキープできる体幹づくりが大切です。
- 登山のために体幹を鍛えるメリット
- マンションでもできる体幹トレーニング

【この記事を書いた人】
- 2021年10月ブログ開設。記事執筆数100本以上。
- サラリーマン。時々、ブロガー活動。
- 登山は日帰り~山小屋泊まで。富士山経験あり。
- Twitter:@Beyond-s16
このブログの中の人も、コロナ禍で自粛した直後の登山で、
体幹の弱さからバテバテになって苦労した経験があります。
登山だけでなく、日常生活でも快適に過ごすヒントになるので、最後まで読んでいってくださいね。
体幹トレーニングのメリットは3つ
体幹を鍛えることで、登山中にはありがたい3つのメリットが得られます。
ロングコースの持久力が付く

結論から言うと、体幹を鍛えることでロングコースにも耐えられる持久力が付きます。
理由は、体幹が安定すると手足が効率よく動かせるので、持久力がアップするから。
登山中は常に段差や傾斜を移動し続けるので、
1歩ずつの足腰への負担が、後半になるほど響いてしまいがちなのです。
腰痛予防になる
登山では、容量が30Lを超えるザックを背負う機会も多いはず。
重い荷物を背負って長時間歩けば、平地で過ごすよりも腰に負担がかかります。
体幹トレーニングでは、インナーマッスルとアウターマッスルを同時に鍛えていくので、
腰痛予防としても期待できます。
下山に強くなる

山が好きな人に聞くと、「登るよりも下る方が苦手」という意見を耳にすることがあります。
その理由の1つとして、体幹への負担が大きいことがあります。
下山中は、足元を踏み外さないように、
登る時以上に足の置き場を探す時間が増えます。
つまり、片足で踏ん張る時間が長くなり、
体幹が不安定だと軸足に負担が増えてしまいます。
これが、下りの方が疲れる原因です。
つまり、片足で踏ん張る時間が伸びるので、体幹が不安定だと軸足に負担が増えてしまいます。
体幹トレーニングで、腹筋や背筋を鍛えることで身体が安定し、軸足にかかる負担も軽減することが期待できます。
体幹トレーニングの4メニュー
ここからは具体的に取り入れているメニューをご紹介します。
メニュー①:プランク
著書「登山ボディのつくり方」などを手掛けた芳須勲さんがヤマケイオンラインで紹介しているプランク。

写真のように、両肩の下に肘をつき、つま先立ちして身体を一直線に保ちます。
まずは20秒から、毎日少しずつ伸ばしていくと腹筋と背筋を鍛えることに役立ちますよ。
この他にも、登山ボディを作るトレーニングのコツは、こちらの本で紹介されています。
メニュー②:スラックレール
体幹が弱っていることを痛感してから買ったのが、スラックレール。
スポンジのような素材のかまぼこ型のレールです。


スラックレールの上に片足立ちするだけですが、最初は難しいかも。
トレーニングは以下の2ステップで進めます。
ステップ1) 右足で立って、左足を前後に振る。左足も同じ。
ステップ2) 右足で立って、しゃがんで立ち上がる。左足も同じ。
ステップ2) 右足で立って、しゃがんで立ち上がる。左足も同じ。
という動きを取り入れています。
平衡感覚の訓練にもなるので、
細いリッジを歩くような登山前の訓練にも合っていると思います。
メニュー③:スクワット
「登山の時にひざや足首が痛くなる」という悩みがある人もいると思います。
そんな時は、スクワットで「太ももの筋肉」を鍛えましょう。
「ひざや足首と関係ないじゃん!」と思うかもしれません。
でも、太ももなんです。
ひざや足首が痛くなる原因は、山道を歩いて着地する時の衝撃が関節に集中するから。
この着地の衝撃を和らげることに、太ももの筋肉が使われています。
太ももの筋肉が疲れて、着地の衝撃に対抗する力が弱まることで、ひざや足首への負担が増していきます。

太もものトレーニングとして最適なのは、スクワットです。
スクワットの動きも、正しい動きをしていないとかえって足を痛めることもあります。
以下のなかやまきんに君の動画が、正しいスクワットの姿勢を分かりやすく解説してくれていますよ。
メニュー④:動的トレーニング
最後は動的トレーニング、つまり身体を動かしながら行うトレーニングです。
Youtubeの「Marina Takewaki」チャンネルの動画を使うことが多いです。
2021年4月にはNHKの「プロフェッショナル 仕事の流儀」にも取り上げられるなど、注目を集めています。
自宅でできるトレーニング、通称・宅トレを当たり前の世界に、というテーマのもとに
毎週トレーニング動画や食事に関する情報がアップされています。
体力アップや呼吸機能の強化にはHIITもオススメ
上でご紹介したのは体幹トレーニングですが、
登山の体力づくりにはHIITというトレーニング法もあります。
HIITとは高強度インターバルトレーニング(High Intensive Interval Training)のことで、
短時間に心拍数が上がる運動メニューを続けます。
スクワットや腹筋など、体幹を鍛えると同時に持久力アップにつながりますよ。
竹脇まりなさんの動画を組み合わせた7日間のHIITプログラムもあるので
こちらから始めてみるのも良さそうですね。
また、プロテインやBCAAなどをトレーニング時に飲むと、筋肉の回復をサポートしてくれて効率的に筋力アップができます。
当ブログでは、飲むタイミングや、飲みにくい時のアレンジレシピもご紹介しているので
最後までのぞいてみてくださいね。


体幹トレーニングの頻度は?
体幹トレーニングの頻度についても、考えておきましょう。
山岳スポーツフィジカルトレーナーの坂主拓國さん監修のトレーニングでは、
次のようにトレーニング頻度が推奨されています。
「1日トレーニングをしたら2日休養」が目安。
2日すぎても筋肉に痛みがある場合は、痛みがなくなるまで日数を置く。
出典:山と渓谷 2021年3月号「筋力強化のトレーニング」より
超初心者は無料体験で教えてもらうのもアリ
「トレーニングなんてしたことない」
「身体を痛めないか、心配」
そんな時は、パーソナルトレーニングなどでトレーナーさんに教えてもらうのもアリです。
オンライントレーニングの無料体験なら、
まずは自宅で、そして無料で試してみることができますよ。

まとめ:オフシーズンにもトレーニング
この記事では、登山向けトレーニングとして体幹を鍛えるメニューをご紹介しました。
中々行けない時期やオフシーズンにも、次の登山を目指してトレーニングしておきましょう。
次の登山が素敵な山行になることを願っています。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
https://beyond-s.com/climb/protein/


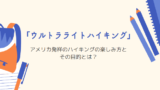



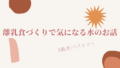

コメント