かつてアメリカ国務長官を務めたヘンリー・キッシンジャー。
ニクソン大統領・フォード大統領の政権時に、東西冷戦やベトナム戦争の外交交渉に携わった人物です。
キッシンジャーは交渉術に長けていたと言われていて、彼が手がけた外交交渉をハーバード大学が総力を挙げて研究した1冊も出ているほどです。
この記事ではそんな1冊「キッシンジャー超交渉術」から、アメリカを軸とした近代世界史、そして史実である外交交渉から学ぶ交渉術のポイントについてご紹介していきます。
- 相談や打ち合わせの予定に不安を感じる時
- アメリカの近代外交を調べたい時
- 冷戦の歴史を知りたい時

【この記事を書いた人】
- 2021年10月ブログ開始。記事執筆数100本以上。
- サラリーマン。時々、ブロガー活動。
- 1か月の読書は5~6冊。
- Twitter:@Beyond-s16
そもそも交渉とは?
そもそも、「交渉」という言葉は精選版 日本国語大辞典では次のように説明されています。
「交渉」ーある事柄を取り決めようとして、相手と話し合うこと。かけあい。談判。
コトバンク(https://kotobank.jp/word/%E4%BA%A4%E6%B8%89-495676)より引用
この説明にもあるように、「交渉」という言葉が指すのは、
「相手と話し合う部分」そして「交渉のテーブル」についた相手との対人的な駆け引きに焦点があてられることが多いです。
この記事で取り上げる「キッシンジャー 超交渉術」の中で、「交渉」という言葉はもう1つの側面を持ちます。
それは、キッシンジャーが用いた「テーブルから離れて」行う戦略です。
この本の序文では、テーブルから離れて行う戦略を次のように説明しています。
そうした戦略には、たとえば、交渉のプロセスに関係者を招き入れたり締め出したりすることや、協調体制を築いたり壊したり、行き詰まりがもたらす結果をより良くしたりより悪くしたりすることが含まれる。
「イントロダクション 最高の交渉者、キッシンジャー」より引用
「交渉」と「折衝」の違い
交渉の類義語には「折衝」があります。
「折衝」ー利害のくいちがう相手と談判やかけひきをすること。また、その談判。
コトバンク(https://kotobank.jp/word/%E6%8A%98%E8%A1%9D-548168)より引用
交渉の中でも、特に相手との利害関係が一致していない場合を「折衝」と呼ぶ、という考え方があてはまりますね。
キッシンジャーは元米国国務長官
この本は、ヘンリー・キッシンジャーという人物の過去の交渉を研究した1冊です。
ヘンリー・キッシンジャーは、アメリカの国務長官や大統領補佐官として、
ニクソン政権やフォード政権の外交に携わってきた人物です。
在職中には東西冷戦やベトナム戦争下で、中国やソ連などと交渉にあたった交渉者です。
この本では、キッシンジャーが経験した外交交渉を研究し、そのポイントをまとめています。
交渉のポイント
値切り交渉はしない
キッシンジャーが述べている交渉のポイントは、「値切り交渉」のようにしないことです。
周りの話でこんな話を見聞きした見たことがないでしょうか。
「交渉相手に到底受け入れがたい要求を突き付けられて、こちらが譲歩するのを待たれている」というようなケース。
こうしたケースでは、お互いに「次の交渉でどこまで譲歩を引き出すか/求められるか」を考えて身構える分、交渉が停滞に陥りやすくなります。
また、以下は当記事の執筆者の意見ですが、
こうしたケースは、お互いに歩み寄って合意を目指しますが、最終的にはどちらかが折れてまとまる場合が多いと思います。
結果として、交渉終了後も良好な関係を続けるのは難しいのでは、と思います。
値切り交渉にしないアプローチとは
キッシンジャーは本書の中で、次のように述べています。
望ましいのは、最初から、最も持続可能と思える提案をすることだ。持続可能な提案とは、すなわち、それを持続させれば双方にとって得になる提案のことだ。
第11章「提案、譲歩、建設的曖昧さ」より
つまり、極端な提案をするのではなく、双方にとってベネフィットをもたらす提案から交渉をスタートすることです。
この方針は、交渉の停滞を避けるとともに、別の効果も生みます。
それは、「(極端な要求に対して)柔軟で、すぐ折れる」という評判が広がることを避けることです。
もし、自分の働いている組織について「柔軟で、すぐ折れる」という評判が業界で流れているならば、
極端な要求をされることが増えていくことでしょう。
目の前の交渉だけでなく、長期的な視点で見ても、
持続可能な提案を最初にすることは重要となるということですね。
ゲームチェンジのための「テーブルから離れた」戦略
交渉相手と利害が一致しない場合、
交渉を重ねても相手が「イエス」よりも「ノー」と言う可能性が高くなります。
こうした場合に「テーブルから離れた」戦略が重要であるとキッシンジャーは述べています。
これは言い換えれば、交渉相手の結論に影響を与える可能性がある動機やプレッシャーを、交渉の席以外で操作するということです。
「キッシンジャー 超交渉術」の中では、かつてアフリカにあったローデシアが現在のジンバブエへと独立する過程を挙げています。
キッシンジャーはザンビアや南アフリカ、イギリスと多国間交渉の末、
白人多数支配となっていたローデシアに圧力を強めていきます。
つまり、ローデシアとキッシンジャー(アメリカ)の交渉のテーブルで動くのでは、
周辺諸外国との交渉によって、ローデシアにとって白人多数支配を続けることの利益を減らしたのです。
キッシンジャーは、こうした「テーブルから離れた」戦略について、次のようにまとめています。
歴史的に見て、交渉者が言葉による説得だけに頼ることはまれだ。一般に交渉における一国の立場は、提案の論理だけでなく、相手が拒んだ時に、いかなるペナルティーを課すかによって決まる。
第6章「ゲームを変えるー合意・不合意のバランスを形成する」より引用
ここでいうゲームは、ゲーム理論におけるゲームチェンジを指しています。
また別の機会でご紹介したいと思いますが、
ゲーム理論の中でも有名な「囚人のジレンマ」について学ぶなら、
次の本が例が多く分かりやすいと思いますよ。
まとめ:「世界史」✖「交渉」を学べる1冊
この記事では、アメリカの元国務長官、ヘンリー・キッシンジャーが手がけた外交交渉を例に
交渉のポイントをご紹介しました。
実際に20世紀に起きた史実の裏側を取り上げているので、アメリカを軸とした近代世界史と交渉術を一挙両得に学べますよ。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。


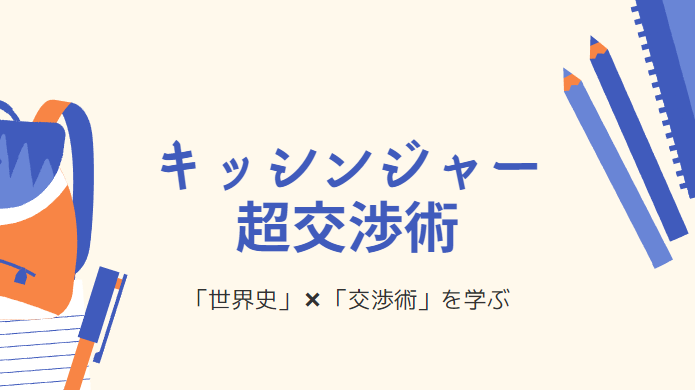


コメント