登山に行く時のドリンク、どうしていますか?
もしもあなたが秋・冬シーズンの登山の準備をしていたり、夏でも2,000mを超える山に行くなら、山頂付近の気温はまず間違いなく10℃台かそれ以下。
温かい飲み物が欲しくなるし、防寒着を持っていく分だけ他の荷物を軽くしたいですよね。
この記事では、メーカーや用途によって重さが大きく変わる登山用ボトルの選び方について、ご紹介します。
登山用ボトルを選ぶポイント
ポイント①:登山で必要な水分量は3時間に1リットル
登山をしている時に私たちの身体から失われる水分の量は、どのくらいかご存じですか。
鹿屋体育大学の山本正嘉教授が2000年に報告した研究では、失われる水分を体重と行動時間から計算しています。(資料の35ページ)
脱水量(身体から失われる水分)[ml] = (体重 + 荷物)[kg] × 行動時間[h] × 5
このブログでも紹介している高尾山の登山コースを例に計算してみましょう。
例えば、
- 体重65kgの人
- 荷物の重さは5㎏
- 高尾山の稲荷山コース(片道90分)を往復 =3時間
とすると、身体から脱水する水分量は1050mlになります。
山本教授も約1リットルの水なら持っていくことができそうですが、行動時間が長いコースを計画している時は、とても持っていけないような量の水分を失うことになりますね。
山本教授は、「登山の行程中で同量の水分を摂るのが難しい場合、最低でも7~8割は飲むことが必要」としています。
行動時間が長い場合は、複数のボトルに分けるなどして用意すると、バランスよく荷造りがしやすいですよ!
ポイント②:保温・保冷機能を付けるか
真夏や真冬の登山の場合、保温や保冷機能が欲しくなる時もあります。
特に山頂でコーヒーや料理に使いたいという人には、保温や保冷の機能が付いているボトルを選んでおくと、短時間で準備がしやすいので重宝しますよ。
保温・保冷性能の目安として多いのが、100℃のお湯、または0℃の水を入れてから6時間後にどのくらいの温度になるか、という書き方。
多くの製品でお湯ならば6時間後に70℃以上、水ならば10℃以下をキープできるので、気になる人は製品詳細を確認しておきましょう!
ポイント③:持っていける重さを超えないか
最後のポイントは、ボトル自体の重さを気にすることです。
最初のポイントでもご紹介したように、荷物が重くなれば身体の脱水量も増えます。
登山の荷物は軽くすることが鉄則なので、自分の体力と相談しながら持っていける重さを超えないか、というポイントでボトル選びもしておきたいです。
例えば、普段からデスクワークが多くて歩く距離が短い、という場合なら、登山用の荷物は4~5kg以内に納められるようにできると良いです。
2つ目のポイントでもご紹介した保温・保冷機能があるボトルは重くなりやすい傾向にあるので、絶対温かくないとダメだ!という用途が無い時は、軽量さに注目してボトルを選ぶのもアリです。
実際に使っているボトルと使用感をご紹介
ここからは我が家で実際に使っているボトルと、使用してみての感想をご紹介していきたいと思います。
[THERMOS 山専ボトル]山頂で開けても湯気が出る抜群の保温性能
最初はサーモスの山専ボトル。
容量は500mlを使っています。
保温性能の高さは際立っていて、さすが「山専」。
朝の出発前に熱湯を入れて、夕方帰ってきてからもフタを開ければ湯気が出る。
製品の公称値としては、100℃のお湯を入れて6時間後でも77℃以上をキープとされています。


使いたいケースとしては、山頂でコーヒーを飲みたい時や汁物の料理をしたい時。
珈琲ならば、ガスバーナーなど使わなくてもそのままホットコーヒーのドリップにも使えます!
標高2,000m以上の山ならば、真夏に登っても山頂は10℃台。
ホットドリンクで身体の芯から温めるのは疲労回復にもつながって重宝します。
ボトルのサイドや底にラバーがついているので、手袋などをしている時も手が滑ることなく取り出しやすい高いデザイン性。
本体の重量も保温機能が付いているボトルとしては軽い290gで、ここでも荷物を軽くしたい登山好きのチェックポイントをしっかり押さえてくれています。
[nalgene 広口ボトル]文庫本よりも軽い!90gの高耐久性ボトル
ナルゲンの広口ボトルは、1970年代からアウトドア用として認知されているロングセラーボトルです。
ご覧の通りの半透明のボトルには保温・保冷機能はありません。
ボトル本体の重さが約90gと一般的な文庫本(150g)よりも軽いので、荷物の軽量化をめざすにはベストなアイテムです。
もともとナルゲンは実験用のプラスチック製品を作っていたブランドです。
軽量でありながら強度も十分で、1,2回落とした程度ではひび割れたりしません。
耐久性は高いですが、7~8年使うと割れやすくなります。
ザックの外側に部裏下げたり、サイドポケットに入れておくと、バスや電車で荷物を降ろすときにぶつけてしまうので、ザックの中に入れるのが安全です。

ドリンク用の他に次のようなアイデアもあります。
- 行動食としてナッツやチップスなどの固形食を入れる
- 濡らしたくない地図やチケットを入れる
荷物が重くなりがちな泊付きの登山など、オールシーズンで使えるボトルですね。
軽量で荷物に入れやすいので、ロードバイクのツーリングなど、他のアウトドアシーンでも必携になりますよ!
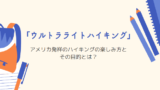

余談ですが、写真の左から2番目、鈴カステラとコアラのマーチを同じボトルに入れると、
カステラの湿気でコアラのマーチのサクサク感が失われます。
サクサク系は1つのボトルにまとめた方が、食感がキープできますよ!
[Klean Kanteen インスレート]細身でザックのポケットに入るスタイリッシュボトル
3本目はアメリカ発のステンレスボトル、クリーンカンティーンのインスレートボトル。
細身でスタイリッシュなデザインで、ザックのサイドポケット、カラビナで吊るす、などどこにでも入れやすい。
キャップが1つだけのデザインですが、保温機能も高いのが特徴です。
製品の公称値としては、100℃のお湯を入れて6時間後でも72℃以上をキープとされています。
朝の出発前に熱湯を入れて、お昼にあけても十分熱いと思えるお湯を持って登れます。
本体の重量は、500mlの山専ボトルより約50g重い345.7g。
重たい理由は容量が592mlと、少し大きいためです。
登山中の水分補給は、1回あたり150~250mlほど飲むというのが目安。クリーンカンティーンの方が1回分弱、多めに水を入れられる計算ですね。


Klean Kanteenのレビューでたまに見かけるのが「水が漏れた」という声。
たしかにしっかりとキャップを締めずに横に倒したりすると漏れてくる場合があります。
心配な時は、キャップを締めてボトルに入れる前に倒したりひっくり返して漏れないことを確認しておきましょう。
Klean Kanteenのボトル選びで注意したいのは、同じ形状で保温機能のあるボトルとないボトルの2つのラインナップがあることです。

ボトルの側面に「INSULATED」と書いてあるのが保温機能のあるインスレートボトルです。
保温機能がないボトルは「INSULATED」と書かれていないので、見分ける時に確認しましょう。
2本以上のボトルを使い分けるアイデア
我が家では登る季節や用途に合わせて、このボトルたちを使い分けています。
使い分けアイデアとして、次のようにシーンを考えています。
真夏・真冬の登山なら保温・保冷機能付き
真夏なら冷たい水、真冬なら温かいお湯を持って行けるボトルを選びましょう。
冬場の登山では、山頂に着くまでに身体も冷えてしまうので、暖かい飲み物で休憩すると身体も心も落ち着きます。
もう少し荷物が増えてもOKならば、ホットコーヒーを山頂で淹れましょう。
写真は、山専ボトルを買う前のものです。

コッヘルでお湯を沸かす → 注ぎやすくするために一度ナルゲンに移す → コーヒーを淹れる
温かいお湯を持って行けないとこれだけの手間がかかりますが、山専ボトルやKlean Kanteenインスレートボトルならば、そのまま注ぐだけでコーヒータイムを始められます。
コーヒードリッパーには写真でも使っているウルトラスポーツのモデルがイチオシ。
軽量で折り畳みもできて荷造り時に楽できますよー!
泊付き登山なら、軽量性を重視
山小屋やテントに泊まる登山、通称・泊付き登山。
着替えや調理器具が必要となり、荷造りするとあっという間に荷物が重くなりますよね。
そんな時はナルゲンの軽量性が役に立ちます。
山専ボトルやKlean Kanteenの重さが300g前後、対するナルゲンは約90gと、差は歴然。
ボトルのように複数持っているアイテムは軽いものを選ぶと、体力温存にもつながります。
山ご飯にはお湯を持っていこう
山頂で調理をする予定なら、お湯を持っていきましょう。
たとえば、こんなチーズリゾットが食べたいとします。

準備はいたって簡単です。
- 玉ねぎ、ベーコンなど切った状態で荷物へ。
- お米は冷ご飯。 ← タッパに入れておくと取り皿にもなる。
- チーズは溶けやすいシュレッドチーズ。
- 具材+お湯をコッヘルに入れてバーナーで10分温める。 ← 時々コッヘルの底から混ぜる。
- 完成!
お湯を使うことで時短レシピになり、寒い思いをする時間も減らせます(笑)
ラーメンなど麺類の調理にも応用できるので、山専ボトルやKlean Kanteenでお湯を持っていきましょう!
ボトルのパッキングはバランスよく
最後に2本以上のボトルを持っていく時のパッキングのコツをご紹介します。
ザックへの荷物の入れ方、「どんな入れ方をしても重さは一緒でしょ」と思う人もいると思います。
バランスよく荷物を入れれば、身体の一部に負担がかかることを避けられますよ。
長距離の山行の時に、左足にだけ負担がかかってつらい、といったトラブル回避のためにも、パッキングは工夫しましょう。
水の入ったボトルは荷物の中でも特に重たいアイテムです。
複数持っていく場合、例えば両サイドのポケットに1本ずつ入れて、交互に飲むと荷物の重さのバランスも変わらず、登っている途中の足腰トラブルも起こりにくいですよ!

また、途中の売店や山荘で水が買える場合は、最低限の水分だけボトルに入れて、残りは途中で調達するのも荷物を減らすアイデアもあります。
自分の登るコースや季節に合わせて持っていくボトルの本数やタイプを選ぶと快適な登山につなげやすいですよ。
まとめ:ボトルを使い分けて快適な登山を
この記事では、登山用ボトルの選び方をご紹介しました。
保温機能が欲しい、軽量さで選びたい、色々な登山シーンに合わせて使い分けられるように、タイプの違うボトルを持っておくと便利ですよ。
寒い時期に登る予定の人は、温かい飲み物で山頂からの眺望と至福の1杯を楽しんでくださいね!
当ブログでは、登山を始める人向けに、まずは揃えたい道具5選もご紹介しています。
「靴やザックなど、まだ買っていないよー!」というあなたは、ぜひ一度読んでみてくださいね!
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!




コメント