このブログの中の人は、大学院で博士課程にいたことがあります。
自分が在学していた時も思いましたが、博士課程に在籍している人自体が少ないので、その進路の話って情報が少ないと感じます。
この記事では「そもそも大学院って何?」ということから、卒業後の進路のことまで、ご紹介していきたいと思います。
工学部の場合なので、理学系や文系の大学院とは違う部分もあると思うので、その点はご了承ください。
- 大学院はどんなところか
- 大学院生のお金の話
- 修了後の進路の選び方

【この記事を書いた人】
- 2021年10月ブログ開始。記事執筆数100本以上。
- サラリーマン。副業としてブロガー活動。
- 某大学で工学博士取得。
- Twitter:@Beyond-s16
大学院には修士課程と博士課程がある
まず大学院って何?という人向けに。大学院は、大半の人が大学を卒業した後に通う学校です。
大学院は修士課程(博士前期課程と呼んでいる大学もあります)が2年間、博士課程(博士後期課程とも)が3年間の5年間程度の学校です。大学と同じで、必要な授業の単位を取れていないと、進級できなかったり、修了できなかったりします。
大学では卒業論文の単位がもらえれば学士号をもらえますが、修士課程では修士論文が合格になれば修士号、博士課程では博士論文が合格になれば博士号をもらうことができます。
修士課程の特徴:授業が割とある
通う大学院によるかもしれませんが、修士課程は大学と同じように講義やレポートがあります。
最近の研究で流行っているテーマをそれぞれ教員が教えてくれる感じだったので、大学の時に受けるただひたすら公式っぽい講義よりは楽しく感じる人も多いかもしれません。
私の通っていた大学院では、午前中に講義があって午後からは研究室に行って自分の研究テーマについて実験したり解析したりしていました。
修士課程は2年しかなく、M2(修士2年)の秋以降は、修士論文を書いたり発表の準備をしたりとめちゃくちゃ多忙になります。
研究室によっては「M1(修士1年)からずっと忙しいよ」って場合もあるので、研究室は慎重に選びましょう。
博士課程の特徴:ひたすら、研究。以上。
はい。博士課程は、もうね、ずっと研究です。
講義もほとんんどないので、研究して、学会で発表して、論文書く。この繰り返しです。
探せば、大学院の中で企画している特別講義みたいなものを受けたりできますが、それが気分転換になるレベルにずっと研究してます。
なぜそんなに研究しなくてはいけないか。
それは博士課程の修了要件に「論文をX本以上発表して、国際会議でX件以上発表していること」と明記されているからです。
つまり、論文を出して、国際会議で発表していないと、どんなに頑張っても博士号がもらえないのです。
(博士号はもらえなかったけど、単位は全部取った!という場合は、単位満了退学という扱いになります。)
私の場合は、論文が中々発表できなくて、D1(博士1年)の冬からD3(博士3年)の夏まで、切れ目なく論文を書き続ける日々が続きました。
論文を英語で書くことに加え、海外での学会発表にも行かなくてはいけなかったので、この時期は英語に苦しんだ時期とも言います。
ちょっと脱線しますが、論文を書くときは、英語の辞書とアカデミックライティングの本があると便利です。
アナログですが、紙の辞書ならジーニアス英和辞典がオススメです。単語の使い方も余すことなく書いてあるし、文例もあるので書きたいことに当てはまるかすぐわかります。
もう一つ、あると便利なのがアカデミックライティングの本です。
アカデミックライティングとは、論文用の英語の表現の仕方のことです。この本だと、論文の各セクションで
- どんな単語を使ったらよいか
- 表現の仕方で査読者がどう受け取るか
とか文例がたくさんあるので、書き方に困った時に助けになりました!
お金の話:特に博士課程になるとお金がない
大学院生、特に博士課程になると、1日の時間のほとんどを研究に費やすようなことになるので、飲食店などのアルバイトをしている人は滅多に見かけません。
結果として、お金がない学生が多いです。
自分の研究テーマをアピールできる学生だと、特別研究員(DC1,DC2)など文部科学省系の研究員に採択されて、給与と研究費をもらえる場合もありますが、とても狭き門です。
博士の学生でも、やりやすいアルバイトは、大学の授業のアシスタントです。
私も大学の授業のアシスタントで週に2コマ(90分×2コマ)働いて学費とか学会の渡航費に充てていました。
それでも当然お金は足りないので、以前の記事で書いたインターネットモニターとか、健康食品の治験とかでお金を貯めていました。
治験のモニターは登録しておくと、簡単なものからハードなものまで紹介が見られます。
病院に10日間入院・検査で○万円、のような高単価なものもありましたが、当然研究が止まるので見送り。
健康食品を毎日摂取して、月に一度健康診断を受けるライトなもので1~2万円もらったことがあります。
博士号取得後の進路:教員、研究員がほとんどで民間は少なかった
博士号取得後の進路ですが、大学の助教や国の研究機関の任期付きの研究員になる人が多かったですが、一定数民間企業に行く人もいました。
民間に行く人は、元々共同研究していた企業にそのまま就職、のように在学中から知っていたというケースも少なくなかったと思います。
研究員志望なら、学会で顔を覚えてもらおう
研究員のポストを探す場合は、JREC-IN portalで研究テーマや希望ポストを書いておくとオファーが来る場合があります。
また、学会などに参加した場合はできるだけ懇親会にも参加して顔を覚えてもらうと、「今度ウチの大学で研究員の募集あるよ」とか教えてくれることがあります!
研究発表や論文で覚えてもらえるのはもちろん嬉しいですが、知り合いを増やす意味でも効果的でしたよ。
民間希望なら、自分で応募先探しを。D3の夏からでも間に合います!
民間希望なら、指導教員が力になってくれない場合もあります。
できるだけ早めに就職サイトに登録したり、企業の展示会に足を運んで、応募先を探しましょう。
企業によっては、修士と博士で初任給が変わらない企業もあるので、気になる方は注意してチェックしましょう!
私も就職活動はD3の8月から始めましたが、11月に応募した就職先で採用が決まったので、遅すぎることはありません。
人手不足が叫ばれているので、夏以降でも新卒採用の募集を受付停止していない企業も多く応募のチャンスは十分。
まずは就職サイトに登録して探してみましょう。
まとめ:D3の夏からでも就職先は見つかる可能性はゼロじゃない!
この記事では、大学院がどんなところか、そして博士号取得後の進路についてご紹介しました。
自分が在学していた時は情報が少なくて困ったこともあったので、この記事が少しでも役に立てばうれしいです。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
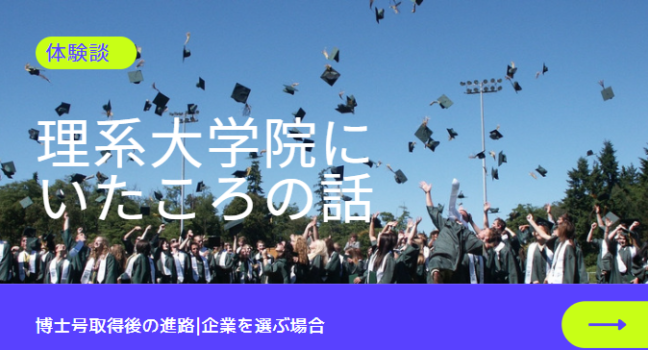



コメント